
※画像と内容は一切関係ありません(汗) |
かつて徳川軍が敗退した上田城を自分
が落としたとなれば、関ヶ原に到着した時
の良い土産になるし、初陣を勝利で飾れ
ば父からも誉められるかも…?
というセコイ考えもあったにちがいない。
「我が軍は4万、上田城は天守閣すらな
い小城(実際、真田軍は2千人だけしか
いなかった)、負ける訳がない!」
と豪語した。
一方、昌幸としても秀忠を関ヶ原に行か
せない為に、何とか相手を怒らせ、戦闘
に持ち込む必要があった。
|
秀忠は上田城に近づくと、徳川の大軍を知れば降伏するかも知れぬと、降伏勧告をさせた。
使者には兄・信之と本多忠勝の子・忠政。会談の場に現れた昌幸は頭を剃り、粛々と降伏を受け入れ開城を約束した。意外にあっさり解決した・・・のか?
秀忠は大喜び。…ところが策士・昌幸、これは巧みな時間稼ぎだった。
その日も、翌日も開城されない。
翌々日、9月5日。関ヶ原合戦は10日後(15日)であり、かなりやばい。。
もうタイムリミットだ。
「これ以上待てん!今一度使者を送って開城を催促して来い!」。
と家臣へ怒鳴るあたりがまだ秀忠の甘ちゃんなところか。
有無を言わさず攻め込むか、無視して関ヶ原へ向かえば良いものを。激昂した秀忠は、とりあえず後者を選択し、全軍に攻撃命令を下した。幸村は「それがし、兄上とは戦いとうない」と、信之が着く頃には上田城に撤退していた。 |
昌幸・幸村がどのような戦術で徳川軍を挑発し、戦ったのかをざっくりとご説明しますと。
まず昌幸と幸村が自ら50騎を率いて城外に出てきた。
総大将が現れて徳川軍はびっくり。
昌幸らは偵察だけして戦わずに城内へ戻って行ったのだ。
これは、総大将が最前線に出てきたのは、“お前らに絶対やられはせん”と嘲笑するのと同じ。
頭に来た徳川軍は一斉に城門へ向かった が、その結果、後方の本陣が手薄になった一瞬の隙を突いて、後方に潜んでいた真田の伏兵たちが秀忠を襲撃した。 |
  |
そこを城内の真田鉄砲隊が一斉射撃!
徳川軍がパニックになると、城門が開いて幸村
の騎馬隊が襲い掛かってきた。
徳川軍は挟み撃ちになってさらに大混乱。
結局、秀忠は一旦、退するしかなかった。
これはいつか来た道。徳川は援軍が到着したが、城の手前の神川は真田側によって上流の堰が切られて大増水しており、渡河して参戦することが出来ない。
真っ赤だった顔色がみるみる真っ青になる秀忠。水位が下がって援軍が合流すると、真田軍は上田城に閉じこもって篭城戦に入った。
城内にはたっぷりと兵糧・弾薬が備蓄されている。
「この城を落としていたら関ヶ原に間に合わぬ…無念」。
秀忠軍は急いで関ヶ原へ向かったが、途中の天候が最悪。
山中で豪雨にあうわ、利根川は洪水寸前だわで、関ヶ原合戦の開戦時間に間に合わないばかりか、到着したのは合戦から4日後の9月19日のことだった。
家康は激怒し、秀忠が合流しても3日間対面を禁じた。 |
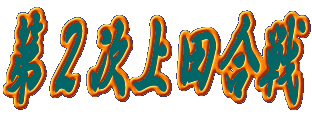
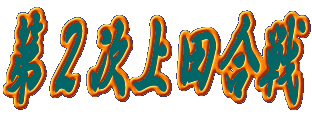
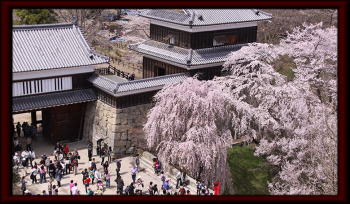

 秀忠にとって、重要なのは関ヶ原であり、真田攻めはあくまでも“大事の前の小事”。
秀忠にとって、重要なのは関ヶ原であり、真田攻めはあくまでも“大事の前の小事”。 真田父子は秀忠軍を翻弄し、遅参作戦は大成功に終わったが、肝心の関ヶ原の方で西軍(石田三成)が敗れてしい、第二次上田合戦に勝利したのに敗将という立場になった2人。
真田父子は秀忠軍を翻弄し、遅参作戦は大成功に終わったが、肝心の関ヶ原の方で西軍(石田三成)が敗れてしい、第二次上田合戦に勝利したのに敗将という立場になった2人。