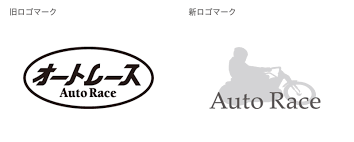監督省庁は競輪と同じく経済産業省(製造産業局)。
小型自動車競走法に基づいて財団法人JKAが運営し、指定自治体がリミュチュル方式による勝車投票券(車券)を販売する。
千葉県と船橋市、川口市、伊勢崎市、浜松市、山陽小野田市、飯塚市の1県6市が主催している。
オートレースにはS級、A級、B級の3つがあります。オートレースで一番強いのがS級が一番強いです。現在S級は48人です。オートレースで準決勝に出るには順位のポイントが高い順に決められます。優勝戦は準決勝の1着2着で決められます。
S級とかに決められるのは半年に1回で年に2回決められます。
オートレースの競走(レース)は通常1日12レース行われます。
1競走の出走数は通常8車で、1周500メートルのオーバルコースを規定の周回数走行することで行われます。
スタートラインはゴールラインの100m後方に存在し、走行距離が100mプラスされる。一般レースは6周回 (3100m)、GI・GIIは優勝戦が8周回 (4100m)。SGは準決勝戦が8周回、優勝戦が10周回 (5100m) で行われます。
選手間に技量差があるためレースの大半がハンデレースで行われます。近況の着順やタイムを参考に番組編成委員によって距離によるハンデが選手へ与えられます。スタートラインを0線(通称ゼロせんまたはゼロハン)と呼び、以下10m毎に最大110mまでのハンデが選手へ課せられます。このため、ハンデレースは有力選手による後方からの追い上げ、比較的軽いハンデ位置からの逃げ切り、2つのレース展開が同時進行します。
選手の技量差が僅差のレース(主にグレードレース)は、0mまたは10m線から8車横一列でスタートするオープンレースで行われます。オープンレースは主にスタート力に優れた選手が逃げ切る展開が多い。SG「日本選手権オートレース」は、全レースがオープンレースで行われます。
開催は3日、4日、5日間の連続開催、勝ち上がり方式で行われレースは一般戦、予選、準決勝戦、優勝戦で構成されます。
試走 選手が枠番順に隊列を組んでコースを3周します。最後の一周は青旗の合図で全力走行が義務付けられています。 これにより競走車の調子等を観客へ見せるのが試走の目的であります。主催者が全力で走行していないと判断した場合は、当該選手のみ再試走を指示されます。 また、選手の自己申告により再試走する事もあります。試走後は主催者より試走タイムが提示されるが、再試走を行った選手の試走タイムには「再試走」と表示される。理由の如何に関わらず、再試走した場合は1回目より速いタイムを出さないと欠車となります。